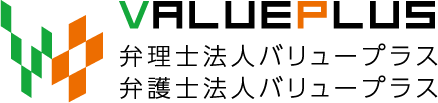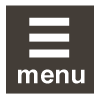| 事務所報 | 発行日 :令和7年8月 発行NO:No55 発行:バリュープラスグループ |
|---|---|
| →事務所報バックナンバーINDEXへ |
【3】映画「字幕」について【同一性保持権】及び【氏名表示権】の侵害が認められた判例紹介(知的財産高等裁判所/令和6年(ネ)第10054号/判決日令和6年12月23日)
文責:弁護士・弁理士 古莊 宏
1.はじめに
「ゾンビ」という外国映画について、依頼を受けて日本語字幕データを制作した字幕翻訳者(=控訴人X)と、さらにDVD・ブルーレイへと商品化して販売を行った被控訴人Y1~Y3との間で、当該字幕に関して、【同一性保持権】及び【氏名表示権】の侵害が問題となった事件である。
以下に、それぞれの判旨について紹介する。
なお、複製権および頒布権侵害についても、問題にはなったものの、Xの許諾があったものと認定され侵害は生じていないとされたので、本稿では省略する。
2.【同一性保持権】について
(1)事実関係
本件Y1らの商品において、「そうだね/テレビはいつも討論だ/ もはや政府がこの事態を/収拾できないことが明らかになり/駄弁を弄している」という翻訳の波線部が、表示されなかったというものである。
(2)判旨
本件では商品にチャプターを設定したことにより字幕が一部表示されなくなっただけで改変は存在しない旨のY1主張に対し、「同一性保持権は、表現が改変されることにより、著作物の表現を通じて形成される著作者に対する社会的評価が低下することを防ぐためのもの」とした上で、「DVDに格納されたデータがオリジナルであるとしても、字幕として購入者等に認識される表現が変更されていれば、同一保持権侵害が生じ得る」と判示した。
また、欠落文字が上記波線部のようにわずか11文字であることからやむを得ない改変(著作権法20条2項4号)である旨のY2主張に対しても、「欠落文言が11文字であるとしても、ひとまとまりの意味のある部分であって。原判決別紙対比表のとおり、欠落部分があることにより、「収拾できない」ことの主体が一義的に明らかとはいえなくなるから、やむを得ないものとはいえない。」と判示した。
(3)考察
同一性保持権の侵害有無の判断において、法政大学懸賞論文事件(東京高裁/平成2年(ネ)第4279号/判決日平成3年12月19日)では、立法当初からの厳格適用説が用いられ、わずかな句読点や中黒の変更でも侵害であるとの判断がされている。
なお、計装工業会講習資料事件(知財高裁/平成18年(ネ)第10027号/判決日平成18年10月19日))では、第三者が必要に応じて著作物に改変を加えることを含めて著作者が黙示的に許諾している場合、著作者の同意に基づく改変として同一性保持権を侵害しないとの判断もされている。
本件では、そもそもXの黙示の同意が認められないケースといえる。
また、本件では11文字を塊として捉えて、主語として文脈の中で果たす役割を吟味している点で、厳格適用説を適用したものでも無いといえる。
本判決では、同一性保持権の趣旨について「社会的評価が低下することを防ぐため」と言及していることから、ベルヌ条約を配慮してか、日本国内における同一性保持権の権利範囲に、少なくとも一定の歯止めをかけようとしているように思料される。
3.【氏名表示権】について
(1)事実関係
本件Y1らの商品において、Xの氏名は表示されていなかった。
(2)判旨
本件では、契約関係にある緊密な関係の当事者間においては、氏名表示権に関し、著作者の権利行使の意思表示がある場合に初めて、他の関係者は拘束される旨のY2主張に対して、「字幕付きの外国映画においては、字幕翻訳者の氏名を表示するのが一般的な取扱いであり(中略)、日本語字幕翻訳を業とする第一審原告が氏名表示の不表示をあえて望むとも考え難い。」との事情を述べた上で、「著作者の名誉・声望・社会的評価、満足感等を保護するため、氏名を表示するか否かの決定を著作者に委ねたという氏名表示権の趣旨からすれば、表示を要しないとの著作者の意思が客観的に認められない限り氏名表示を要するというべき」と判示している。
なお、直接商品制作には関わらず販売だけに関わったY3について、「(商品の)ジャケット以外(エンドロール等)に字幕翻訳者の氏名が表示されているかどうか、仮に表示されていないとすれば字幕翻訳者が望まなかったのかどうか、疑問を抱いてしかるべき客観的状況であったといえ、一般消費者又はレンタル事業者に販売する前に、これらの疑問について第1審被告(中略:Y1のこと)に対し確認すべき注意義務があった」として、過失を認定している。
(3)考察
本件については、字幕翻訳者に対して、穏当な判断であったと思料する。
(令和7年8月作成: 弁護士・弁理士 古莊 宏)