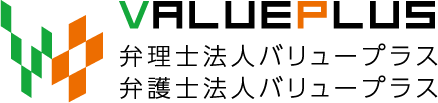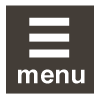| 事務所報 | 発行日 :令和7年1月 発行NO:No54 発行:バリュープラスグループ |
|---|---|
| →事務所報バックナンバーINDEXへ |
【1】侵害警告について
文責:弁護士・弁理士 溝上 哲也
1.はじめに
バリュープラスグループでは、特許・実用新案・意匠・商標の調査及び出願の業務のほか、これらの権利や著作権、肖像権、育成者権、不正競争防止法上の権利について、侵害の停止又は予防を求めたり、損害賠償を請求したりする侵害警告案件についての業務を多く取り扱っています。
侵害警告案件において、権利者側では、次のような請求を行い、侵害を指摘された側では、侵害の有無を争ったり、その権利自体の無効を主張したりして、対抗することになります。なお、これらの請求項目のうち、信用毀損による損害賠償は、特段の事情がある場合に限られますし、謝罪広告は、業務上の信用を害した例外的な場合に認められるにすぎないことに注意する必要があります。
(1)差止請求
①製造・販売・輸入の中止
②侵害品の廃棄・設備の除去
(2)損害賠償請求
①消極損害/逸失利益の賠償
②積極損害/侵害調査費用・弁護士費用
③無形損害/信用毀損による損害額
(3)信用回復措置請求
①謝罪広告
本稿では、このような請求をする場合に行われる侵害警告の意義と方法を掘り下げて論じてみたいと思います。
2.侵害警告の意義と方法
(1) 侵害警告の意義
侵害警告案件における侵害警告を定義すると「侵害者に差止請求権の行使が認められている場合に、その行使方法として差止等の請求の意思を表示すること」になります。ここでは、法的手続への移行や損害賠償請求を予告するので、一般に「警告」と呼ばれています。根拠となる権利としては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、不正競争防止法上の権利などがあり、請求の内容としては、製造・輸入・販売の中止など侵害の停止又は予防を求めたり、損害賠償金の支払催告のほか、輸入元、販売先、個数・単価について事実報告を求めることが多いです。侵害警告に際して、これらの事実報告を求めるのは、権利者側では、誰が侵害の元締めかどうか判っていないことが多く、また、損害賠償をどれぐらいの金額で請求したらよいかについても不明であるので、その基本的な事実関係を聞き出す必要があると考えるためです。
(2) 侵害警告の方法
侵害警告の方法としては、通常、次のような方法があります。
①文書
最も多く利用される方法で、通常は、証拠を残すために、配達証明を付けた内容証明郵便を送付して行います。弊所においても、原則はこの方法によっています。内容証明郵便は、資料を同封できないので、特許公報などを送付する必要性が有る場合は、別途書留郵便を送付したり、証拠としては不完全ではあるものの、全部をレターパックで送付したりする場合もあります。
②メール
文書を郵送するには、相手方の住所を把握していることが必要で、内容証明郵便を使えるのは、日本国内だけですから、相手方が海外在住、オークション個人の場合などでは、代替的な手段として、電子メール・SNSないしWebサイトを通じて行うことになります。これらの通知手段の場合は、後日のために証拠を確保しておくことにも注意すべきです。
③口頭
これは、侵害者の店舗や事務所を訪問して、面談の上で行う方法や、電話により行う方法となります。このうち、訪問面談が有効であるのは、同時に侵害品の販売状況などの事実確認ができたり、侵害者に予告を与えず、回答を迫ることができる点です。訪問面談時には侵害品を購入し領収書を受領して証拠を確保した後に、侵害警告を行うことや、複数のメンバーで訪問し、相手方の回答を記録しておくことも肝要です。
(3) 侵害警告に別途の要件が必要とされる場合
侵害警告を行うにあたっては、通常、どのように行うかの縛りはありませんが、特許法などの規定により、次のとおり、特別の要件が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
①実用新案権に基づく差止請求及び損害賠償権の行使
実用新案権は無審査で登録となり、特許・意匠・商標の各権利と異なり故意過失の推定規定がないため、実用新案法29条の2で「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」と規定されていますので、実用新案技術評価書を提示して警告することが、行使の要件となっています
②特許出願公開に基づく補償金請求権の行使
特許権は設定登録後に損害賠償請求ができますが、発明が公開された後は、特許法65条で、「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。」と規定されているので、この場合は、発明の内容を記載した書面を提示して警告することが請求の要件となっています。
③商標設定登録前の金銭的請求権
商標権は設定登録後に損害賠償請求をすることができますが、商標法13条の2が「商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。」と規定されているので、設定登録前であっても、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告した場合は、侵害者の使用によって生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができます。
3.侵害警告書受領時の対応について
侵害警告の意義とその方法・留意事項は、上述したとおりですが、逆に他社から侵害警告書が送られてきたときには、どのような対応をすべきなのでしょうか?
まず、次のような事実確認と方針の策定が必要となります。
①権利内容の調査
特許権などの産業財産権の場合は、まず、登録公報、審査経過、登録原簿謄本を取寄せ、警告の根拠となる権利の権利期間内かどうか、権利者や実施権者が誰かを確認をします。次に、自社の商品や製造方法などが侵害となるか確認するため、その権利の範囲を画定します。またその際にその権利について無効原因の有無を確認します。そのためには、周辺登録の公報や類似検索ないしキーワード検索で他社の公報なども取り寄せることになります。
②対象商品の確認と対比
次に、侵害となった場合の影響などを評価するため、侵害を指摘された自社商品の売上、粗利、在庫、販売先などを確認し、見本、企画資料などの証拠を確保し、担当者、デザイナー等へのヒアリングを実施します。これらの結果を踏まえて、自社商品と権利内容を対比し、侵害かどうかの検討を行います。
③対応方針の策定
さらに、これらの資料や検討結果に基づき、警告者が競争手段、金銭取得、牽制、訴訟準備のいずれの目的で警告したのか把握・推測した上、侵害の可能性の高低と無効原因の有無を斟酌して、侵害を認める方向か侵害を争う方向かの大きな方針を策定することになります。そして、その方針と理由、侵害となった場合の影響などに基づいて、社内体制をどうし、外部専門家への依頼をするかどうかを決めていくことになります。
4.侵害警告相談のご活用
この記事をお読みの事業者の皆様が侵害警告案件に直面された場合には、本稿で論じた事項を考慮して、事案にあった対応をしていただくことが必要と言えます。
弊所バリュープラスグループは、侵害警告案件に多くの経験がある弁護士・弁理士が在籍しており、事業者の皆様と一緒になって、これらの対応に必要な調査や支援をすることができます。侵害警告案件にかかわる知的財産係争相談は、弊所では、1件3万円(税別)で対応しておりますし、侵害警告案件を代理人として対応することも可能ですので、侵害警告案件に直面された場合には、是非、弊所に相談されることをご検討ください。
弊所の知的財産係争相談を利用される方は、お問い合わせフォームにご記入の上、ご連絡くださるようお願いします。折り返し、弊所からご指定の方法でご連絡させて頂きます。
(R7.1作成: 弁護士・弁理士 溝上 哲也)